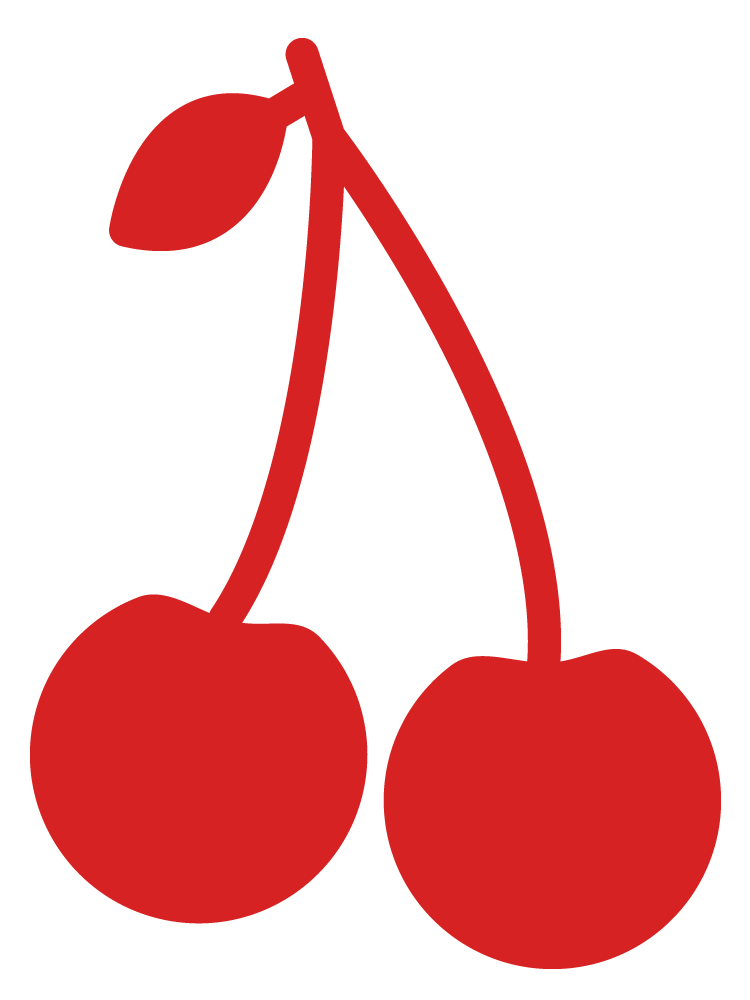――探究者の座、アゼムが『かわったもの』を蒐集している。
エメトセルクのもとに一般市民からの投書があったのは今朝のこと。
開かれた公正なる十四人委員会、という今月の標語にあわせ、アーモロートの善き人たちは委員会の運営に特に協力的である。常であれば遠慮してしまうような些細な意見も汲み上げたい、という意図ではじまったこの取り組みだったが、彼のもとに届くのは相変わらずアゼムの行状ばかり。いつもなら「パシュタロットにでも通報しろ」というようなものが集まるが、そこも遠慮がない。仮面の着用義務違反から買い食いの報告まで、軽犯罪どころかアカデミアの校則違反にも満たない、当代アゼムへのお気持ち表明が、何故かエメトセルク宛てに寄せられてくる。まるで「しっかりと監督しておけ」と言わんばかりに。
確かに彼らの付き合いが長いことも、アゼムがエメトセルクを便利に活用していることも、広く市民に知られていることではある。が、仮にも十四人委員会の中ではアゼムこそが先輩。何故、エメトセルクが彼女の面倒を見ることが当然のように認識されているのだろう。いっそこれがすべてヒュトロダエウスのイタズラであって欲しいとすら思う。
(私はアゼムの保護者ではないのだが……)
彼女の世話を焼くことが、嫌いなわけではない。他の誰かを頼るくらいなら自分を頼ってほしい、とも思う。
正確にはこの関係性に、保護者・被保護者、という名前をつけることに抵抗を覚えるようになっただけなのかもしれない。
今日もアゼムは元気にアーモロート市中を巡り歩いて、人々の心と心を繋ぐ仕事をしている……はずだ。彼女にしかできないその仕事はとても繊細で、難しい。高等技術を要するものではないかもしれないが、尊重されるだけのことを彼女は成してきていた。他の誰かに攫われてしまう前にどこかに隠してしまいたい、そんな昏い思いがふとした隙に忍び寄ってくることもあるが、彼女の笑顔は一人で独占するには眩しすぎる。たくさんの人に愛でられてこそ、真の美しさを見せる花、といったところか。
気は進まないものの、目にしてしまったからには投書を握りつぶすわけにもいかない。が、わざわざアゼムを呼びつけるような緊急性も感じられなかった。どうせ彼女は夕方になればカピトル議事堂に帰ってくるのだ、その際に尋問して、問題があればその『かわったもの』とやらも押収してしまえばよい。
ひとまずは投書は脇においておき、エメトセルクは自身の職務へとその意識を切り替えた。
* * *
夕刻、いつものようにアーモロート市中の巡回を終えてカピトル議事堂に帰着したアゼムを出迎えたのは、不機嫌そうなオーラを隠しもしない不愛想な親友、エメトセルクであった。アゼムの執務室の前で待ち構えていた彼は、赤い仮面の下ではいつものように眉間に深い皺を刻んでいるのだろう。彼女を見つけるなり、深いため息をつく。
(あれ……私、何かしてしまった……?)
今日は特に、彼に咎められるような失敗を犯した記憶はアゼムにはない。善き人の手本として、堂々と市中を闊歩していただけだ。多少の大立ち回りは演じたが、論より証拠が彼女のモットー。終わりよければすべてよし、とまでは開き直らないが、三方丸く収めた自信がある。だからアゼムは堂々と、昨日ぶりに顔をあわせた男にむけて「ただいま」と手を振った。
「おかえり、と出迎えてやりたいのはやまやまなんだがな」
と、彼は手にした紙をひらひらと振って、肩を落とす。何やら文字が書かれたそれは、様式からしてどうも投書のようだ。なるほど、いつものようにアゼムに対する相談がエメトセルクに宛てられた、というところだろう。彼も全部真に受けずにさらっと流してしまえばいいのに――元凶でありながら、彼女は他人事のように彼の気真面目さを嘆く。
「おまえが変なものを集めている、と投書があった。疑っているわけではないがな、そういう通報があったからには確認だけはしておきたい」
と彼は当たり前のように手を差し出してきた。寄越せ、というポーズだろう。
が、残念ながらアゼムには心当たりがない。
正確に言うならば、心当たりしかない。
ありとあらゆるものをコレクションすることは彼女のライフワークといってもいい。とはいえ法に触れるようなものは集めていないし、職務の一環として得たものはすべて委員会に報告のうえで所有している。少なくとも他者にどうこう言われる類のものでは、ないはず、だ。おそらく。たぶん。エメトセルクの前に立つと自信がなくなってしまうのは不思議なもので、いつも彼に叱られている、いや彼に守られているが故なのだろう。アゼムが多少の無茶をしても咎められなくなったのは、エメトセルクという庇護者の絶対的信頼によるところが大きいことは承知している。
「それは勿論、協力するけれど。でも、本当に、叱られるようなものを集めた覚えはないよ? 君に見せられないようなもの……あったかな」
たいていのものは、集めた末にエメトセルクとヒュトロダエウスに自慢するのだ。遅かれ早かれ露呈し、怒られる、そんなものを集める意味がない。誰にも見せられないものなんて収集しても――そこまで考えて、一つ、思い当たる節がないでもないことに気が付いた。悪いことではない、一般市民から見れば奇異に映るかもしれない、誰に見せても恥ずかしくはない、がエメトセルクにだけは――恥ずかしくて見られたくないもの。まさか、あれがバレたというのだろうか。
「アゼム?」
急に挙動不審になった彼女を訝しむように、エメトセルクはその様子を探ろうとする。仮面をまだ外していなくて助かった。目があったが最後、彼の圧に負けて、あることないこと自白してしまわないとは言い切れない。
「い、いえ、なんでも、なんでもないよ。でも本当に、倫理的に問題のようなものは集めていないの。アゼムの座に賭けて、誓える」
「そのあたりは信用している、おまえはなんだって最終的に私とヒュトロダエウスに自慢するんだ。今見せても後で見せても、まあ驚きの度合いが変わる程度で問題はないだろう? 投書があったからには念のため確認だけはさせてくれ」
エメトセルクの言うことはいちいち正論で、どうにも彼を誤魔化すことは難しいらしい。
こうなったらそれのことを指していないことを祈るしかない、と思いながら、自室に繋がる扉を開く。
「とりあえずどれのことでも、この部屋にあると思うから、入って。さすがにプライベートなことだから、廊下で話すのは憚られるの」
「構わない、邪魔をするぞ」
アゼムがエメトセルクの執務室を、創造物管理局の局長室を我が物顔で使うように、彼もそれなりにこの執務室には熟知している。アゼムが大切なものをどこにしまっているのかも、言わずとも知っているはずだ。それでも彼は絶対に、アゼムにお伺いをたてる。親しき中にも礼儀あり、といって、一線を、引く。彼の行いは善き人の手本として完璧なはずなのに、どこか物足りなく感じる自分に、近頃苛立ちを覚える。
「集めているものなら、いつもの引き出しにあるから。で、どれのことを言っているの? 流石に全部出せ、なんて言わないでしょう?」
アゼムは年代物の戸棚の扉をコツコツと叩いた。中には彼女が長い年月をかけて集めたものが、空間拡張されて収められている。すべて取り出すには部屋の広さも時間も足りないし、非効率的だ。投書には一体何と書かれていたのだろう。
「投書には、おまえが植物を集めているようだ、とあった。本のようなものに挟んで保存している、と」
嗚呼、なんでこんなことだけはドンピシャで当たってしまうのだろう!
それはまさに、アゼムがエメトセルクだけにはナイショにしておきたかった、秘密のコレクションのことに違いない。誰にも見せたことはないはずなのに、誰にも話したこともないはずなのに、いったい誰がこれのことを知ってしまったのだろう。ごく稀に外に持ち出しては眺めていたのを目撃されていたのだろうか。恐る恐る彼を見上げても、いつもと変わらぬ赤い仮面があるだけだ。
自分から仮面を外して、しょんぼりとした己の素顔を晒す。乙女の秘密を暴くことを、少しは思いとどまっては――くれなさそうだ。
「心当たりは……あります! ありますから! ……笑わないでくれる?」
「笑ってほしいなら笑うが、笑うなと言うなら笑わん。呆れない、という保証は、まあできないが……」
「ですよねー」
戸棚に手を突っ込み、強く念じると、一冊の分厚い本がアゼムの手に吸い寄せられる。感触でそれと認識すると、そのまま空間から腕を引き抜いた。ずっしりと重さのある赤い革表紙の厚い本は、外から見れば何の変哲もないアルバムのように見える。
躊躇いながらアゼムが表紙を開くと、ぺちゃんこになって色褪せた花が一輪、保護フィルムに覆われた状態でその姿を現した。
アーモロートの外れでよく見かける、なんの変哲もない黄色い花。一年を通して咲く、繁殖力の強い、いつだって見られるそれ。エーテルに解いて、星に帰してしまえばいいはずなのに、鑑賞に堪えないその姿で留め置く。その収集はなるほど、一般的な善き人の感性では理解できるはずがない。まさしく当代アゼムの奇行と言えよう。それでもエメトセルクは何も言わない。彼女が見出した何らかの意味を、恐らくは必死に量ろうとしてくれている。
分厚い紙を捲ると、今度は別の花が同じように保存されていた。次のページも、また次のページも、特に珍しくもない花が続く。保存状態の悪いものもあれば、同じ種類のものまであった。
アゼムが手を動かす度、エメトセルクが何かを言いかけて、止まる。十ほど目にしたところで、何を集めていたのか気が付いてしまったのだろう。彼はじっと、彼女の指を見つめていた。
そして彼は座の証である赤い仮面を外し……同じほどではないが赤くなった素顔を晒した。
ひどく照れた様子の彼はバツが悪そうにアゼムから視線を逸らすが、怒ったり、呆れている、といった様子は見られない。それが少しばかり救いではあったが、恥ずかしいのはこんなものを、後生大事に押し花にして保存していることがバレたアゼムの方である。
これらはすべて、アゼムがエメトセルクから贈られた、野の花。
アゼムが花が好きだと知って、折に触れては髪に飾ってくれた花。執務室に生けてくれた花。誕生日にくれた花束。
出会った頃から全部、保存してある。最初と、最近とでその意味合いは大きく変わってしまっているけれど。
「こんなもの、とっておかなくても、またいつでも贈ってやるのに……」
耳まで真っ赤に染めて、目も合わせず、ぶっきらぼうに告げるエメトセルク。でも捨てろ、とは言わない。彼はアゼムが大切にしているものを、自分なりに理解しようとしてくれているようだった。それが何よりも、心を温かくする。
「ただの花なら星に帰してしまえるけれど……君との思い出は、星には帰したくなかったのだもの」
エメトセルクにバレてしまったのは恥ずかしかったけれど、彼との思い出が大切なものであると伝えられたこと、拒絶されなかったことは結果としてアゼムにとってプラスになった、のかもしれない。
開き直った彼女は、一つ一つ、これはいつエメトセルクがくれたものなのか、本人相手に制止されるまで懇々と語り続けた。
その日を境に、エメトセルクが彼女に贈る花が少し、変わった。
珍しい花だったり、豪華な花びらの花だったり、アゼムの好きな色の花だったり。
アゼムの集めるものが「変なもの」扱いされないように、という彼の気遣いなのだろう。
気持ち悪いから集めるな、とは言われなかったことに、アゼムは胸を撫でおろすのだった。
投書に対しては「害のあるものではなかった」というエメトセルクの確認コメントが発表される。
送り主は、長い菫色の髪を指で遊ばせながら(我ながらいい仕事をした)とほくそ笑むのだった。